


お子さんから「今日は学校を休みたい……」と言われると、保護者様としては心配になってしまうこともあるでしょう。体調不良であれば「治るまで休ませよう」と判断できますが、理由をたずねても話してくれないときには、どう対応したらよいのか悩んでしまいます。
子どもたちが学校を休みたがる理由はさまざまです。体調不良の他にも、勉強についていけなかったり、人間関係や学校という環境に慣れなかったり、一人ひとり違います。注意しなければならないのは、大人たちが勝手に「怠けている」と判断してしまうことです。
休みたい理由を話してくれなかったとしても、まずはお子さんに寄り添ってあげましょう。

ひと昔前は「学校は何が何でも行く場所」という認識があったかもしれませんが、現代では「学校を休むこと=悪いこと」ではありません。休まなければならないときはたくさんあります。体調不良、冠婚葬祭、災害、感染症……。この場合は、休まざるを得ない状況といえるでしょう。
学校へ行くことよりも優先すべきことがある場合は、休む必要があります。体調不良の場合は治すこと、冠婚葬祭では家族、災害の際は身の安全を確保することなど。特に感染症を発症した場合には、感染拡大をおさえるためにも欠席すべきとされ、出席停止扱いになることも。
学校を休むときにはどんな理由であっても正直に先生に伝え、嘘をつくことは控えましょう。

子どもたちが学校を休む理由は、休まざるを得ないもの、精神的なものなどさまざまです。学校を休むことは悪いことではありませんが、保護者様はそれぞれの理由に合わせて対応をしていけるとよいでしょう。
体調不良の場合は学校に行きたくないのではなく、「行くことができない」が正しい解釈です。「学校に行きたくないからついている嘘」と決めつけずに、体を休ませてあげましょう。
登校時間を過ぎるとなぜか元気になることもあるかもしれません。嘘を疑いたくなりますが、本当に一時的に体調不良になっていた可能性もあります。学校へ行くことが大きなストレスとなり体の症状として出ているのであれば、それだけつらい状況だとわかってあげることが必要です。
冠婚葬祭や法事は学校を休む正当な理由として、先生も理解し承諾してくれます。忌引きの場合は学校や地域によって異なりますが、公欠(公認欠席)扱いになることがほとんどです。亡くなった方との間柄によって、休める日数が決まっていることがあります。
忌引きで休みたいときは、わかった時点で早めに先生へ申告をしましょう。香典を出してくれる場合もあるので、忌引き明けには先生にあいさつをするとより丁寧です。
学校で居づらいと感じて、学校を休みたくなってしまう場合もあります。その理由の一つが、人間関係です。クラスメイトや先生との関係が良くないことは、子どもたちにとって大きなストレスとなります。
他には、学校という環境が苦手ということもあるでしょう。集団行動が苦手だったり、新学年など新しい環境に対応することが苦手だったりすることで、精神的に疲れてしまいます。小さなストレスが積もって、学校が居心地の悪い場所となってしまっているかもしれません。
学年が上がるごとに、授業の内容はどんどん難しくなってきます。授業についていけなくなると、勉強が嫌いになってしまい、勉強をしたくないという理由で学校を休んでしまうことも。
もともと授業についていけていない状態でさらに学校を休むことで、余計に勉強内容がわからなくなるという悪循環になってしまいます。そのまま不登校になることもあるため、お子さんが「勉強したくないから休む」と言ったときには注意深く見守ってあげましょう。
いつもは元気に学校へ行っているお子さんが突然「休みたい」と言ってきたときには、生活習慣に問題がなかったかを確認してみましょう。スマホやゲームを夜遅くまでやっていて寝不足になり、翌朝の眠気とだるさから休みたくなっている場合もあります。
あるいは、嫌いな授業があって気が乗らず、学校へ行くことが面倒だと思っているかもしれません。「眠いから」「面倒だから」は学校を休む理由にはならないので、行くように指導をしてあげましょう。
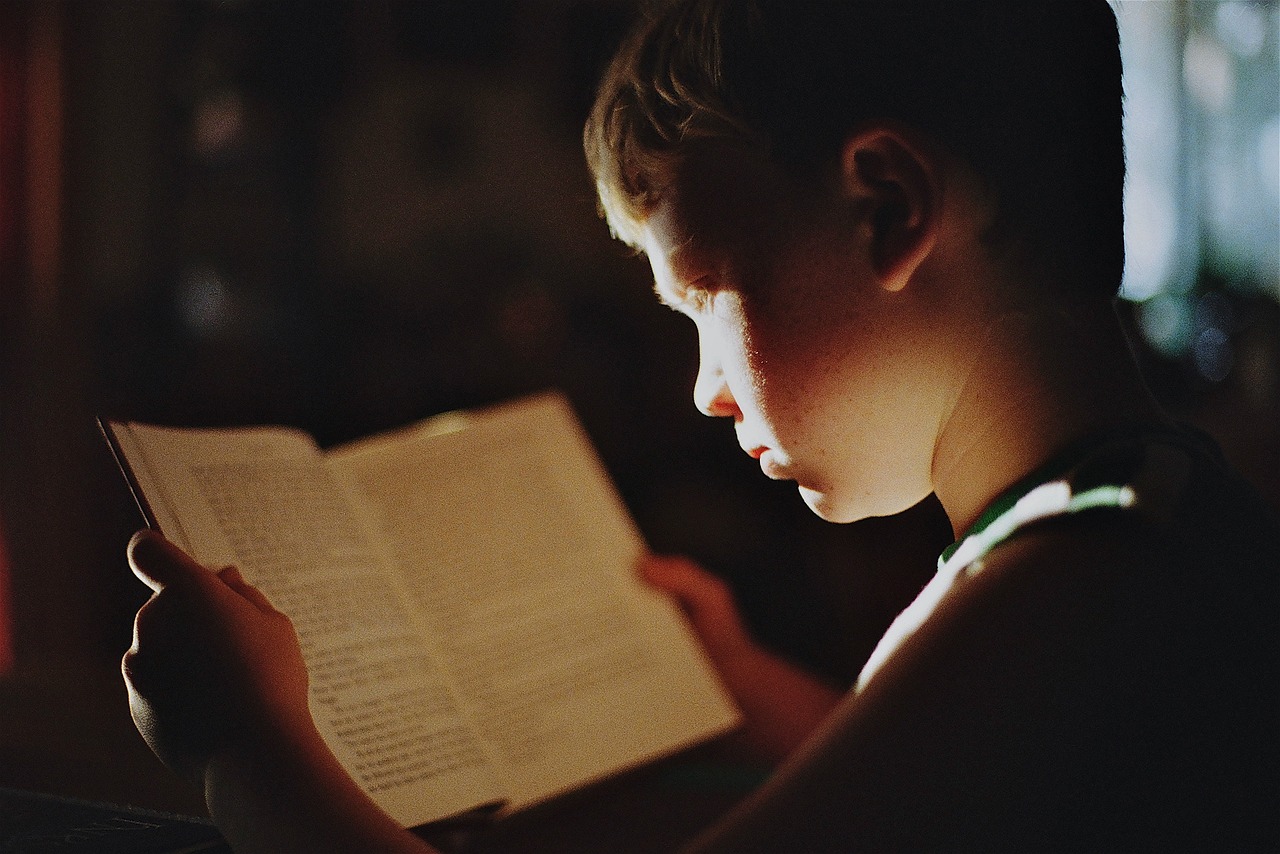
学校を休む理由が何であっても、先生には正直に伝えて、お子さんを休ませてあげることをおすすめします。お子さんが休みたいと思う理由は、もしかしたら学校で何かトラブルや嫌なことがあったからかもしれません。保護者様はお子さんの学校での様子がわからないからこそ、先生と連携して原因を見つけてあげることが必要です。
適当な嘘をついて学校を休むと、お子さんが学校に行ってからも、つじつま合わせにまた嘘をつかせることにもなりかねません。そして、バレた場合には先生との信頼関係が崩れてしまいます。お子さんのためにも、先生との信頼関係はとても重要です。無駄な嘘はつかず、正直に先生に伝えて、学校と協力してお子さんを見守りましょう。

学校を休んでも欠席扱いにはならず、公欠や出席停止になることがあります。登校が困難な場合、受験や公式戦に行く場合、正当な理由があれば欠席にはなりません。どんなパターンが該当するのか、詳しく見ていきましょう。
災害時や交通機関に問題が生じて登校できない場合は、欠席ではなく公欠扱いになります。その理由は、学校が生徒の安全第一を優先し、自宅待機が最も安全と判断するからです。大きな災害が起きた場合は、出席停止扱いになることもあります。
登校するには危険と感じる場合には、身の安全を確保することを優先して、無理に学校へ行かないようにしましょう。災害の場合は、学校から登校に関して通知が来ていないかも要確認です。
学校や自治体で決められた感染症や難病を発症した場合は、出席停止扱いになります。身近なものでは、インフルエンザやコロナウイルスが挙げられるでしょう。人が集まる学校では感染が拡大しやすいために、完治するまで欠席を強いられます。
出席停止扱いを受けるためには診断書が必要な場合もあるので、学校の規定を確認し、必要であれば病院で発行してもらうように依頼をしてください。欠席にはならないので、発症したときには安心して療養に専念してください。
オープンキャンパスなどの学校行事や、クラブチームの公式試合へ参加するために学校を休む場合は、公欠扱いになることが多くあります。学校や自治体の規定、大会の規模によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
昨今では小学校や中学校の部活動が廃止され、校外のクラブ活動が盛んになる傾向があります。クラブチームへ所属する子どもたちが増えてきているため、試合のために公欠扱いになる場面も多くなっていくことでしょう。
受験のために学校を休む場合は、公欠扱いになることがほとんどです。受験のための願書を出す際、先生に書類を準備してもらう必要があることも多く、学校側も受験日は把握しています。しかしながら、事後報告になってしまうと認められない可能性もあるので、事前に受験日と欠席する旨を、先生へきちんと申告しておきましょう。
注意点として、「遠方の学校を受験するために前乗りをしたい」という場合、受験日当日しか公欠扱いにならず移動日は欠席になることもあります。

大きな理由はないけれど、「疲れやストレスがたまっているからリフレッシュしたい」など、どうしても学校を休みたいときがあるかもしれません。一日くらいであれば、休む言い訳を用意しておくと便利です。
頭痛は風邪をひいたとき以外でも、疲れや気圧の変化など、さまざまな要因から発生します。「頭痛持ち」の人がいるほど、頭痛は身近な体調不良です。発熱していなくても起こる症状のため、言い訳として使えます。
腹痛は症状によっては動けなかったり、トイレにすぐ行けるようにしておきたかったり、自宅から出られない状況になります。腹痛もまたよくある体調不良の一つであり、誰しもが経験することなので理解が得られやすいことが利点です。
体質によって違いはありますが、女性の生理の際は貧血、腹痛、頭痛、腰痛、吐き気などさまざまな症状があります。症状が重い場合には動けないほどつらいものの、その程度は周りの人にはわかりづらいものです。
女性ならではの生理痛とあって、先生も症状を詳しく聞いてくることはほとんどありません。生理中は体調不良に加えて情緒が不安定になることもあります。周りからも「無理せずゆっくり休んでね」と言われることが多いでしょう。
貧血はめまいや動悸を引き起こすこともあり、無理をして登校すると学校で倒れてしまう可能性があります。倒れるとけがをしてしまう心配もあるので、先生からは「自宅で休むように」と言われるでしょう。
幼いうちは鉄分の消費量が多いことから、貧血になりやすいともいわれています。よくあることとして先生も認識しているため、理解が得られやすい理由です。ただし、多用すると学校生活で常に先生に心配をかけてしまうことになるので注意しましょう。
熱が37度以上あれば、発熱とみなされる傾向があるようです。微熱で症状があまりなかったとしても、正当な休む理由になります。朝は微熱だったとしても、昼にかけて徐々に上がる可能性も考えられるため、「微熱なら登校しなさい」と指導する先生はいないでしょう。
発熱は数日続くことが多いので、「一日休んだけれど、どうしてももう一日休みたい」という場合にも使えます。学校を連日休みたいけど正直に理由が言えないときに、使いやすい言い訳です。
「家庭の事情で休みます」と伝えれば、先生はすぐに受け入れてくれて、それ以上理由を聞いてくることはないでしょう。さまざまな家庭があり、プライバシーもあるため、先生が詳しく尋ねることは避ける傾向にあります。
ただし家庭の事情も多用すれば、「家庭で何か問題があるのではないか」と先生に余計な心配をかけてしまいます。家庭訪問を提案される、学校を巻き込んでの大きな出来事になってしまうといった可能性もあるため、ほどほどに使うようにしましょう。
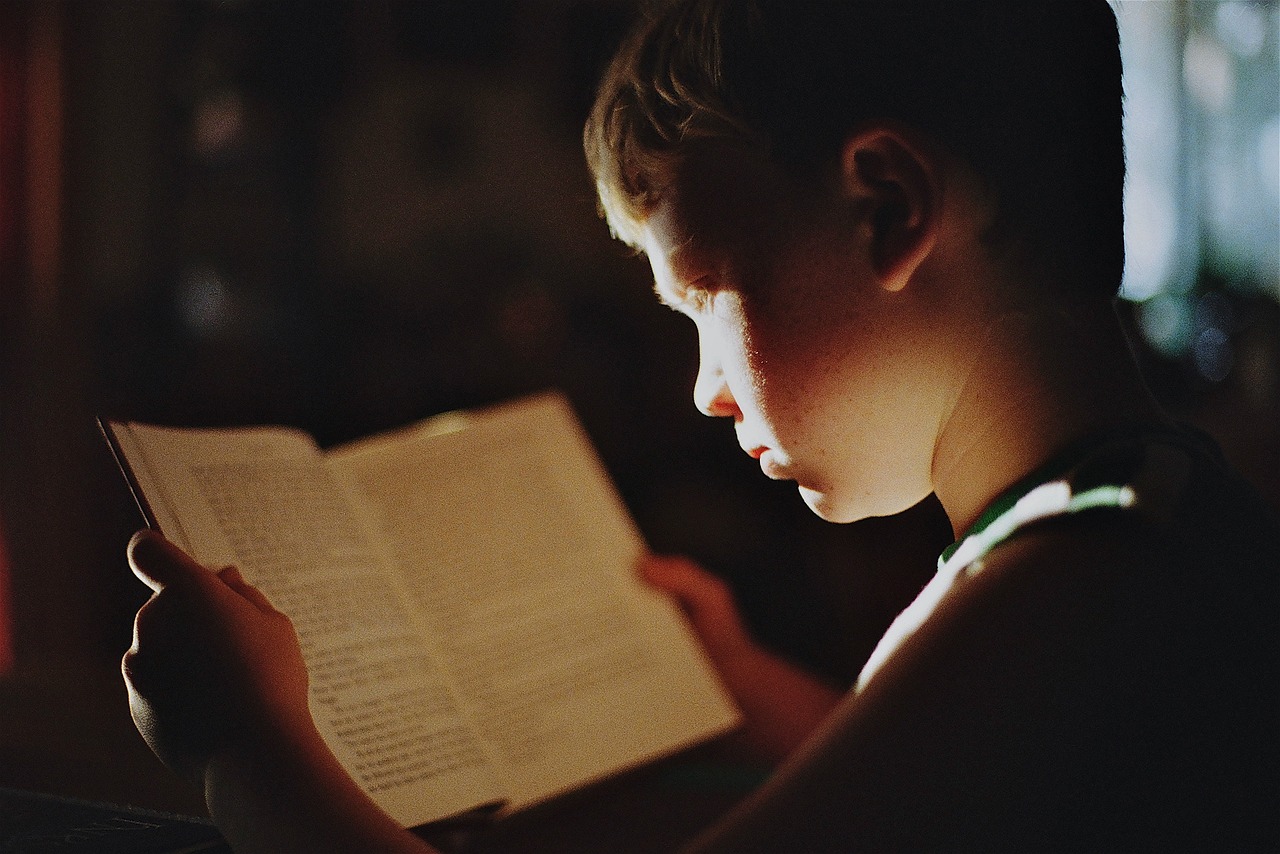
体調やメンタルを整えるために、ズル休みをしたくなるときもあるでしょう。しかしながら、ズル休みを続けてしまうと、たくさんのリスクを抱えるということも理解しておかなければなりません。ズル休みがもたらすデメリットを詳しく説明していきます。
子どもたちは「学校は簡単に休めるものだ」と認識すると休み癖がついてしまい、その結果として不登校になる可能性があります。学校を休むことは悪いことではありませんが、あまりにも休むことが多くなると出席日数が足りないという事態にもなりかねません。
学校を年間30日以上欠席すると不登校とみなされ、受験のときに不利になることがあります。お子さんに無理を強いるのは良くありませんが、休み癖がつくことでリスクがあることを認識しておきましょう。
嘘をついてズル休みしたことがバレてしまうと、「この人は平気で嘘をつく」と認識されて信頼を失い、学校生活にも影響を与えるかもしれません。嘘をついて休むと、学校に行ってからも嘘をカバーするために、また嘘をつかなければいけなくなります。嘘に嘘を重ねていけばいつかボロが出て、バレてしまうものです。
学校での人間関係が崩れてしまうことによって学校へ行けなくなるリスクもあります。お子さんに嘘をつかせないためにも、なるべく正直に理由を伝えて休むようにしましょう。
学校を休む頻度が多くなっていくと、「嘘をついてズル休みしているのでは」と疑いの目で見られるように。すると、本当に休みたいときにまで嘘を疑われてしまうこともあるでしょう。
たとえば体調不良と嘘をついて学校を休み続けた場合、本当に発熱して数日間寝込むときにも「また体調不良?」「本当かな?」と思われてしまうかもしれません。また欠席日数が多くなると出席日数が足りなくなるリスクもあるため要注意です。
学校を休むことで勉強に遅れが出てきて、授業についていけなくなるリスクがあります。すぐに追いつけるなら心配はいりませんが、授業の内容がわからない状況が続くのは大きなストレスとなるでしょう。
勉強が嫌になって「学校へ行きたくない」と休んでしまい、さらに授業についていけなくなるといった悪循環になりかねません。宿題がたまってしまうので、ズル休みをするとその分やることが増えてしまうことも理解しておきましょう。

お子さんから「学校を休みたい」と言われると、どう対応したらよいか迷ってしまいますよね。休ませていいのか、行かせるべきか、先生に相談すべきか…心配は尽きません。大切なのは、お子さんに寄り添ってあげること。保護者様ができることを詳しく解説していきます。
「学校を休みたいのは甘えだ」と決めつけず、お子さんに理由を聞いてみましょう。もしかしたら学校で何か問題を抱えていてストレスを感じていたり、精神的な負荷から体調不良になっていたりする場合もあります。
理由を教えてくれなかったとしても、まずは学校を休ませて、お子さんの気持ちが少し落ち着いてきたタイミングで改めてたずねてみましょう。問い詰めたり責めたりしないように、お子さんの不安を解消できるような聞き方を心がけるとよいです。
お子さんの休みたい気持ちを尊重し、しっかり休ませてあげましょう。学校を休むことへの罪悪感から「無理にでも行かせた方がよいのでは」と思うかもしれません。しかしながら、無理強いをするとお子さんは「責められている」と感じ、精神的に追い詰められてしまうことにもなりかねません。
お子さんからの「学校へ行きたくない」は、保護者様へのSOSである可能性もあります。まずは学校を休ませて、心と体をしっかりと休ませてあげることが大切です。
早寝早起きなど、お子さんが規則正しい生活を送れるようにサポートしましょう。生活習慣が乱れてゲームなどで夜更かしをしていると、翌朝起きられずにだるさとイライラから学校を休みたくなってしまいます。
スマホやゲームへの依存傾向を感じる場合には、ルールをなるべく早く作ることがおすすめです。ゲームをやっていい時間を決めたり、寝る時間と起きる時間を決めたりなど。一方的にならないよう、一緒に相談して決めるとお子さんも行動に移しやすくなります。
保護者様が抱え込むのではなく、学校や先生と協力してお子さんを見守っていきましょう。学校での子どもたちの様子は、保護者様たちにはどうしてもわかりません。お子さんが学校でストレスを感じるようなことがあるのならば、先生と連携することでその原因をスムーズに見つけることができます。
連携をとるためにも、学校を休むときには嘘や言い訳をせず、お子さんの状況や理由を正直に伝えましょう。先生との信頼関係を築くことも、保護者様にできることの一つです。
お子さんが夢中になれるものを見つけたら、とことんやらせてあげましょう。お子さんは学校を休むことに対して、少なからず罪悪感を感じています。「自分は悪いことをした」と自己肯定感が低くなり、自信がなくなっている状態にあるかもそれません。
好きなことに打ち込み成功体験を持つことで、「自分でもできるかもしれない」と自信を取り戻すことにつながります。まずは自己肯定感を上げて、前向きな気持ちにさせてあげることが重要です。

学校へ行きたくないのは精神的な要因によることが多いため、気持ちを前に向かせてあげることが重要です。ここからは、学校へ行くモチベーションを上げるための方法を3つご紹介します。お子さんに合う方法が見つかるかもしれません。ぜひ試してみてください。
「学校から帰ってきたら、一緒にホットケーキを焼こう」のように、お子さんのテンションが上がる小さなご褒美を用意してあげることがおすすめです。帰った後の楽しみがあると、学校へのモチベーションが保てるかもしれません。
ただし、お小遣いや何かを買ってあげるなど、金銭的なご褒美は避けましょう。頑張りがお金で評価されると、「自分の行動は金銭的な価値」という認識を持つかもしれません。ご褒美がもらえてもお子さんの気持ちは満たされないので注意しましょう。
得意な科目や、簡単な問題、復習から始めるなど、お子さんが手をつけやすいものから勉強することがおすすめです。問題が解けて「自分でもできる」と思えるような成功体験を作ることで、まずは勉強するモチベーションを上げていきましょう。
勉強することに対して気持ちが前向きな状態であれば、苦手な科目や難しい問題にもスムーズに取りかかることができます。やらなければいけない勉強は他にもあるかもしれませんが、まずは得意なもので気持ちを乗せるという方法を試してみてください。
良かったことも悪かったことも、なんでも話せる友人がいると、学校での過ごし方は大きく変わります。味方がいるという安心感は、子どもたちにとって大きな力になります。
隣で一生懸命頑張っている友人の姿を見ることで、「自分もがんばろう」と刺激をもらうこともできるでしょう。友人はときにライバルにもなりますが、なんでも話せるような関係であれば、切磋琢磨しあえてプラスにはたらきます。そんな友人を持てるといいですね。

学校へ行くモチベーションを上げるためには、お子さんが夢中になれるものを見つけ、成功体験を繰り返すことが必要になります。成功体験を作りやすいプログラミングは、子どもたちにおすすめの習い事です。
プログラミングは「正常に動く」というゴールが明確であり、実際にプログラム通りに動くことで成功が目に見えるという特徴があります。学びが成果となって実感しやすいため、成功体験を増やしたい場合にはぴったりの習い事です。
プログラミングスクールの「プロクラ」では、ゲームソフトのマインクラフトの世界でプログラミングが学べるため、子どもたちが楽しんで夢中になれる環境が整っています。学ぶ楽しさと成功する達成感を、プロクラで体験させてあげませんか。
COLUMN