
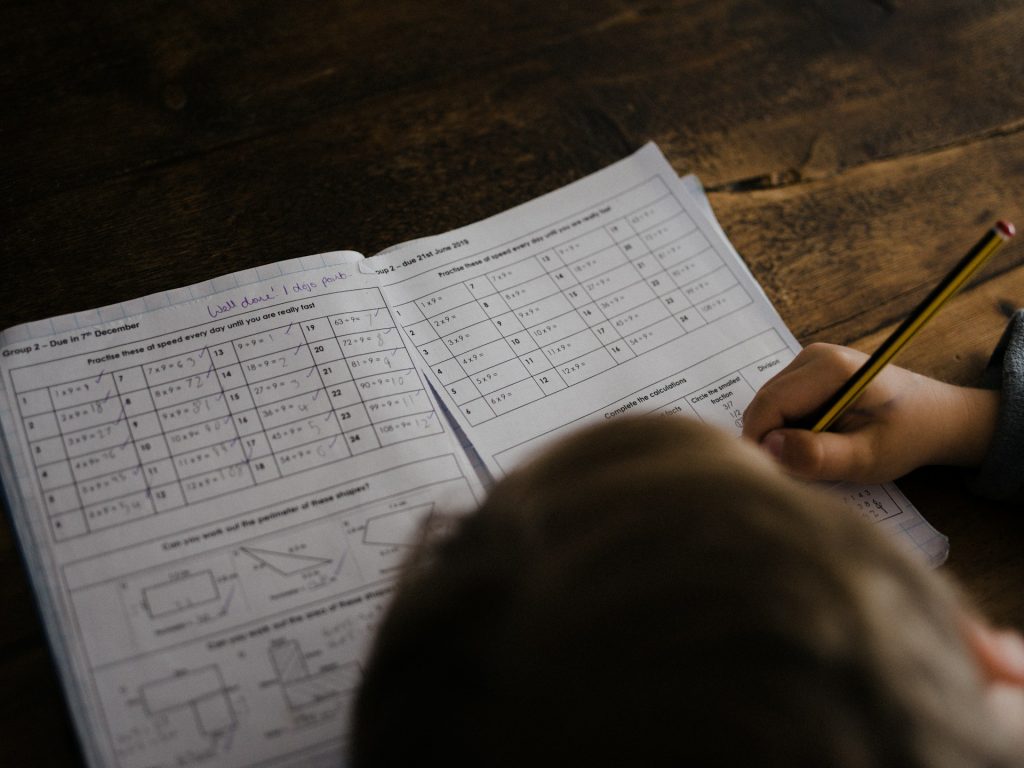
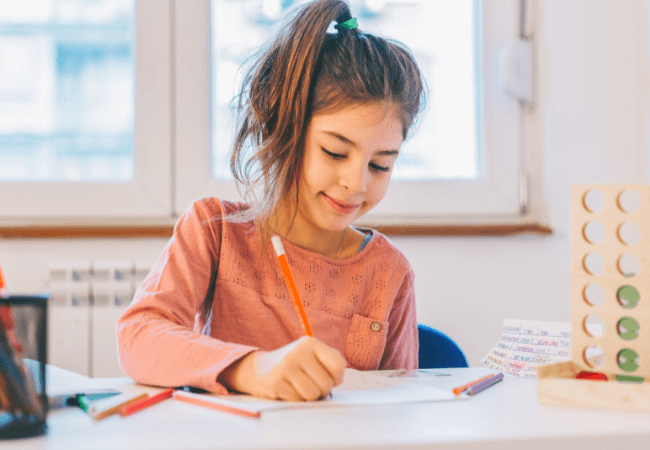
宿題として「自学」を出されると、何をやれば良いのかわからずに手が止まってしまう……そんな経験はありませんか?とくに小6になると勉強量が増えて内容も難しくなるなかで、どうやって勉強方法を決めるか迷うことも多いはず。
やり方が決まらないまま自学を続けようとすると、モチベーションが下がりお子さんが「今日はもういいか」とサボってしまうことも。それが積み重なると学習習慣が途切れ、成績にも影響を及ぼすかもしれません。
この記事では、小6にぴったりの「毎日続けられる自学ネタ」をご紹介します。「楽しい」「達成感がある」「負担が少ない」を大切にした内容なので、すぐに取り組めるだけでなく、続けやすい内容です。自学ネタにお悩みの方は、ぜひ参考にされてくださいね。
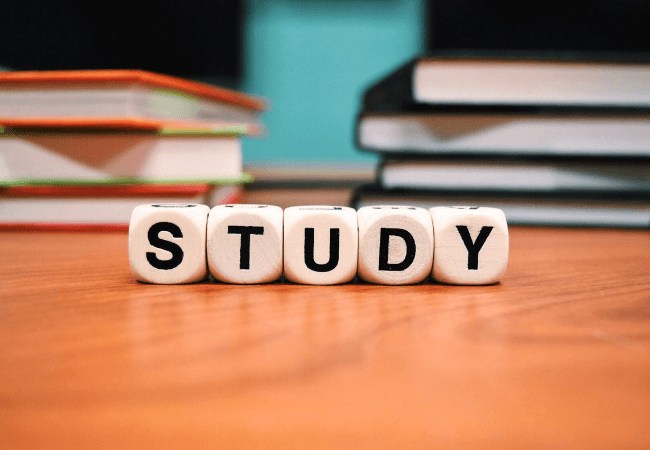
忙しい日々の中で、自主学習を毎日続けるのは難しいですよね。ここでは、自主学習を楽しく、そして確実に継続するためのコツを具体例とともに紹介します。自学ネタを選ぶ前に、まずはお子さんと一緒にチェックしましょう。
小学校高学年の子どもたちが集中力を持続できる時間は、およそ30分といわれています。そのため長時間の学習は負担が大きく、途中で飽きたり疲れたりする原因になることも。短時間の自主学習であれば気軽に取り組めるため、毎日続けやすくなりますよ。
たとえば「漢字を5つ覚える」「計算問題を3問解く」「10ページだけ本を読む」など、短時間で終わる自学ネタがおすすめです。短時間で達成できる内容を選ぶことで「続けること」を無理なく習慣化できます。
はじめから大きな目標を立てると、達成できなかったときにやる気を失う原因になります。小さな目標であれば達成しやすく成功体験を積めるので、次の学習にもつながりやすいですよ。
たとえば「今日は新しい単語を5つ覚える」「ドリルを1ページ進める」など、小さなステップに分けましょう。「ちょっと頑張れば達成できそうな目標」を設定することで、子どもたちはモチベーションを保てるはず。小さな目標をくり返し達成していくことで、無理なく学習の習慣を作れます。
勉強中に余計な雑音が聞こえたり、視界に他のものが入ったりすると、気が散って効率が下がってしまいます。勉強する時間はテレビを消して、机の上には学習に必要な物だけを置くようにしましょう。
また、スマホやゲーム機などの誘惑物の対策も必要です。誘惑物は勉強する部屋には入れないようにして、物理的に距離を置くことも大切です。環境を整えることで「勉強モード」に切り替えられ、集中して取り組めるでしょう。
興味がある内容の勉強はやる気が湧いて、学習に対する抵抗感は減るものです。自学ネタがなかなか決まらないお子さんは、好きな教科の中からヒントを得ると良いでしょう。
たとえば、算数が好きならパズル問題を解く、理科が好きなら観察記録を取る、国語が得意なら短い読書感想文を書く、などが挙げられます。お子さん自身が楽しめる内容をぜひ取り入れてみてくださいね。好きな教科から自学ネタを見つければ学びが楽しくなり、毎日の自主学習を継続しやすくなります。
長い時間勉強していると、疲れて集中力が途切れることがありますよね。集中力をキープするためにはこまめな休憩をとり、頭をリフレッシュさせることが大切です。
自主学習に取り入れたいのが「ポモドーロ・テクニック」です。25分間集中して学習し、5分間休憩するという時間管理法です。自主学習に取り入れると、勉強と休憩にメリハリができて集中力をキープできますよ。自主学習を継続させるためには、集中力をキープできるようにこまめに休憩をとりましょう。
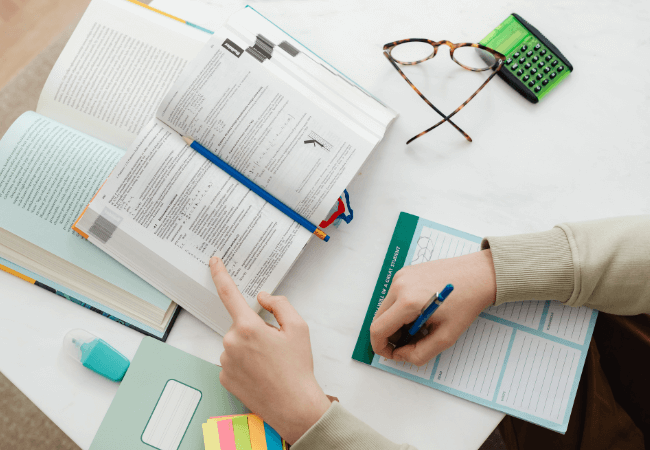
内容が難しい自学ネタでは「自学って面倒」「もうやりたくない」と感じてしまいますよね。ここでは、小6にぴったりの「すぐ終わる自学ネタ」を21個ご紹介します。お子さんに合った方法を見つけて、ぜひご家庭で取り組んでみてくださいね。
読書感想文を書くには、物語の要点を把握し自分の考えを整理することが必要です。このプロセスをくり返すことで、理解力や表現力が自然と向上します。
たとえば、好きな児童書などを読み「本を選んだきっかけ」「どんな部分が心に残ったか」「登場人物の行動をどう思ったか」などをまとめてみましょう。最後まで本を読まなくても、読んだところまでの内容で問題ありません。短い感想文なら15分程度で書けるので、毎日の自学ネタにぴったりです。
中学生や高校生になると敬語を使う場面が増えてくるので、小学生のうちから敬語のルールを整理しておくと良いでしょう。とくに、よく使う言葉の敬語を理解して使い分けられると、日常会話で役立ちますよ。
たとえば「食べる」の敬語表現(尊敬語は「召し上がる」、謙譲語は「いただく」、丁寧語は「食べます」を表にしてみましょう。例文やシチュエーションも一緒にまとめると覚えやすいですよ。敬語の整理は、実用的で知識が身につきやすい自学ネタなのでおすすめです。
熟語の意味をまとめると言葉の成り立ちや使い方がわかり、文章を読むときや自分の意見を表現するときに役立つでしょう。
たとえば「改善」「熟読」「対策」など日常で使う熟語を選び、辞書で調べて意味を書き出します。さらに、それを使った短い文をつくると実践的な練習になりますよ。三字熟語や四字熟語をまとめてみるのも良いでしょう。熟語の意味をまとめることは、短時間で取り組めるので、ちょっとした空き時間に最適な自学ネタです。
ことわざや故事成語を調べると、昔の人の知恵や教訓を知ることができます。作文や会話の中で活用すると、自分の意見をより的確に表現することができますよ。
たとえば「猿も木から落ちる」「犬も歩けば棒に当たる」など、表現がおもしろいものを選んで由来や使い方をノートにまとめましょう。イラストを添えてことわざの意味を整理すると、記憶にも残りやすくなりますよ。ことわざや故事成語は面白さを感じられるため、飽きずに続けられる自学ネタです。
計算練習をくり返すことで、スピードと正確さが向上します。基礎が固まると応用問題にも取り組みやすくなり、テストや日常学習でも大いに役立つでしょう。
とくに分数の四則計算は、苦手意識を持っている人が多いです。中学校でも連立方程式などの単元で引き続き学ぶので、今のうちに苦手意識を無くしておきましょう。毎日数問ずつでも続けることで、大きな成果が期待できます。計算ドリルは、算数の力を少しずつ積み上げられるシンプルで効果的な自学ネタです。
テストの際に問題を解くのに時間がかかり、見直しの時間が足りなかったり、本来解けるはずの問題に手が回らなかったりした経験はありませんか?解くスピードの遅さが課題である場合、自学のときから時間を意識することが大切です。
とくに計算問題はスピード勝負です。タイマーやストップウォッチを活用して記録をつけてみましょう。前回よりも早く解けるようになると達成感もありますよね。時間を意識することで楽しみながら計算力がアップできるでしょう。
平面図を書くと、図形への理解力や空間認識力が高まります。図形の特性を視覚的に学ぶことができ、問題を解く際の作図スキルが向上しますよ。
たとえば、小学校で習う「正方形」「長方形」「三角形」などを書いて、平面図形に慣れておきしょう。平面図形の面積や角度を求める問題が出たときに図形を迷いなく書くことができ、情報を整理しやすくなりますよ。いろんな平面図を書くことは、図形問題を解く際に役に立つおすすめの自学ネタです。
立体図形は頭でイメージする必要があるので、苦手意識を持っている子どもたちは少なくありません。立体図形のおすすめの勉強法は、展開図を書くことです。展開図を書くためには立体を分解して考える必要があるため、空間的なイメージを鍛えるのに効果的です。
立方体、三角柱、円柱などを選び、展開図をノートに書いてみましょう。色を塗ったり実際に切り取って立体に組み立てたりすると、さらに理解が深まりますよ。図形学習をより実感的に学べる楽しい自学ネタとしておすすめです。
植物の成長日記をまとめると、観察力と記録力が身につきます。日々の成長を記録することで、変化を見つける力が養われ、理科への興味も深まるでしょう。
成長日記を書くときには、写真やスケッチを添えて、変化したところや成長段階に合わせた気づきを書いてみましょう。お世話をしてきた植物の成長の様子がわかると、充実感や達成感がありますよね。植物の成長記録をまとめることは、観察するやりがいや楽しさを実感できるため、自学にぴったりです。
人体の臓器名は、小6で習う分野です。臓器の名前や役割をしっかり覚えて、体の仕組みについて理解を深めていきましょう。
まずは、図鑑などを参考にして人体のイラストを描きます。次に「心臓」「肺」「肝臓」などの臓器の働きを簡単な文章で記入しましょう。色をつけるとよりわかりやすいですよ。教科書をただ眺めるよりも、自分で書いた方が記憶にも残りやすいですよね。人体の臓器名をまとめることは、理科の予習・復習にも役立つ自学ネタです。
天体を調べることで地球以外の世界に目を向け、理科の学びを深めることができます。子どもたちは、宇宙のスケールの大きさに感動を覚えるでしょう。
たとえば太陽系の8つの惑星を一覧表にして、名前や大きさなどの情報をまとめてみましょう。惑星のイラストも添えるとさらに楽しく、視覚的に覚えることができます。天体の名前や大きさをまとめると、宇宙への興味が高まるはず。知識を得られるだけでなく学びの広がりを感じられるので、自学ネタとしておすすめです。
絶滅した生き物のなかには、人間による森林伐採、乱獲、土壌汚染などが原因で絶滅した種類も。絶滅した背景を調べることは、子どもたちが「自分にできることは何だろう」と考えるきっかけになります。
また、普遍的に人気な「恐竜」を題材にするのも良いでしょう。学びながら地球の歴史に触れられるので、自由研究にも応用できますよ。絶滅した生き物を知ることで、生物の進化の歴史や自然の変化に興味を持つきっかけになるでしょう。
歴史は覚える内容が多いので「テスト前に暗記するだけ」という学習になりがちですが、暗記だけに頼るとテスト後に内容を忘れてしまいます。そのため、歴史年表をつくると歴史の流れを覚えやすくなりますよ。
たとえば縄文時代から古墳時代までの重要な出来事をピックアップし、簡潔に表にまとめましょう。時系列にまとめることで複数の出来事の関連性を把握しやすくなり、歴史の全体像を理解できます。歴史年表をつくることは、テスト対策や予習復習にも役立つ自学ネタです。
偉人たちはそれぞれの時代に大きな功績を残しています。彼らの行動や考え方を学ぶことで、歴史的な背景を理解するだけでなく、自分の価値観を見つめ直すきっかけになります。
たとえば、坂本龍馬について調べ「なぜ彼が日本の近代化に貢献できたのか?」と考えると、幕末の社会情勢や彼の革新性に触れることができます。調べた内容について感想を書くのも良いでしょう。歴史上の偉人について調べることで、学びの幅が広がり考える力が育つので、自学ネタにぴったりです。
地域の特産品や特色に詳しくなると、地元への理解が深まります。地元の良さを語れる力が身につき、より愛着がわくようになるでしょう。
たとえば「北海道の乳製品」「静岡のお茶」「沖縄のゴーヤ」など、住んでいる地域の特産品をピックアップしてみましょう。特徴や歴史、生産方法などを調べてノートにまとめれば、社会科の学習にも役立ちます。地域の特産品や特色をまとめることは、学びとともに地元をより好きになれる自学ネタです。
有名な観光地について調べると、地理や歴史の知識が広がります。観光地は文化や歴史が詰まった場所が多いため、調べることでその背景に触れる良い機会になるでしょう。
たとえば「富士山」「姫路城」「厳島神社」などを選び、その場所の特徴や成り立ちを簡潔にまとめてみましょう。歴史を学ぶことで、今後その場所を訪れたときにより充実した観光ができるかもしれません。有名な観光地を調べることは、旅行気分で楽しく取り組みやすい自学ネタです。
世界遺産を調べると、世界の文化や自然に対する理解が深まります。世界遺産には人類の歴史や自然保護の重要性が反映されているため、調べることで広い視野を得られるでしょう。
まずは前提知識として、世界遺産の概要、世界遺産の種類、日本の世界遺産などをまとめましょう。さらに、自分の気になる世界遺産をピックアップして特徴や保護活動について調べれば、理解が深まりネタも尽きません。世界遺産を調べることは、文化や歴史を感じられる自学ネタです。
新聞記事を切り抜いてスクラップをつくると、社会の動きへの理解が深まります。また、興味のある内容について深く調べることで、思考力や表現力も高められるでしょう。
スクラップを作るためには、まずは興味のある記事を切り抜きノートに貼りましょう。そして記事の要約や自分の意見、調べたことをまとめます。新聞の名前や日付も記入しておくと、あとで見返したときにもわかりやすいですよ。身近なテーマを選べるので、自学ネタとしても取り組みやすい活動です。
自分で作れる料理のレシピを調べることで、家庭科の知識と生活力が向上します。さらに、調べるだけではなく実際に作ると、家族にも喜ばれますよ。
自学ノートには、用意するもの、手順、作ってみた感想などを書いてみましょう。あわせて注意点や改善点を書いておくと、次回に生かせるでしょう。実際に作った料理の写真を添えると華やかになり、達成感を得られますよ。自分でつくれる料理のレシピを調べることは、家庭科の楽しさを感じられる自学ネタです。
英語で日記を書くことで、表現力と英語力が同時に鍛えられます。身近な出来事を表現するため、単語や文法の復習が自然にできます。
まずは、日付や曜日を自学ノートに書きましょう。「〜に行った」「〜を食べた」などの短い文章から始めると書きやすいですよ。わからないことは辞書などで調べていくうちに、少しずつ表現の幅も広がるでしょう。英語で日記を書くことは短時間でできるため、毎日の習慣にも取り入れやすい自学ネタです。
単語帳を眺めるだけでは記憶が定着しにくいです。単語を覚えるためには、インプットとアウトプットをくり返すことが大切です。
単語をインプットする際には、声に出しながら単語を書くようにしましょう。教材に付属のCDがついている場合は正しい発音を聞くのもおすすめ。手だけではなく耳や口も使うことで、より覚えやすくなります。さらに、答えを隠して単語テストを行えば記憶も定着します。単語を書くのは地道ですが、確実に力がつくので定番の自学ネタです。

いろいろな教科の自学ネタをご紹介してきましたが、選ぶときに気をつけたいことがあります。ここでは、自学ネタを決めるときの注意点を紹介します。お子さんが無理なく継続して取り組めるように、事前に確認しておきましょう。
短期間で終わる一時的なテーマだと、継続が難しく自学が単発になりがちです。習慣化できるテーマなら、少しずつ進めながら成果を積み重ねられます。
たとえば「毎日漢字を3個覚える」「ドリルを1日1ページ進める」など、小さなステップをくり返すテーマを設定すると、無理なく続けられます。1日に進めた量は少なく感じますが、長いスパンでみると、「ちりも積もれば山となる」です。子どもたち自身が「やればできそうだな」と思える自学ネタを選ぶことで、無理なく習慣化できるでしょう。
興味を持てない内容だと自学を苦痛に感じやすく、途中でやる気を失ってしまいますよね。興味のある分野であれば、自然と調べる意欲が湧き、継続しやすくなります。
たとえば「好きな動物の特徴を調べる」「好きな本の名シーンをまとめる」など、お子さんがワクワクする内容を選んでみてください。「やらされている」と感じがちな家庭学習も、自分の好きなことなら前向きに取り組めるはず。興味のある分野から選ぶことで、楽しく学べるでしょう。
勉強は始めるまでが大変ですが、一度波に乗れば集中して取り組むことができます。ただしいきなり難しいテーマを選ぶと、いつまでもその波に乗ることができません。まずは、簡単な内容から始めて成功体験を積んでから次の課題に取り組むようにしましょう。
たとえば「1日の出来事を10行以内にまとめる」「算数ドリルの基礎問題を解く」など、短時間でできる内容がおすすめです。徐々にレベルアップできるよう、初めは無理のない内容を選びましょう。
学校で認められないテーマだと、提出後に評価されなかったり、訂正を求められたりするかもしれません。トラブルを避けるために、事前に適切な内容であることを確認しましょう。
たとえば、自学の内容は自由だと思っていたけれど、塾でやっている課題を自学にするのは禁止だったというケースもあります。せっかく提出したのに認められないと、子どもたちもやるせないですよね。事前にルールを確認し、判断に悩む場合は担任の先生に聞いて自学ネタを決めましょう。
「自由研究のように何かおもしろいテーマの自学をしたい」と考える子もいるかもしれません。しかし、テーマ選びに時間をかけ過ぎると自学の時間が減り、取り組む前にやる気を失うこともあります。
自学ネタを考えるのに時間がかかりそうな場合、「簡単な単語を10個書く」「好きな食べ物について調べる」など、すぐに始められるテーマを選びましょう。悩むよりもまず行動に移せる自学ネタを選ぶことで、スムーズに学習をスタートできます。
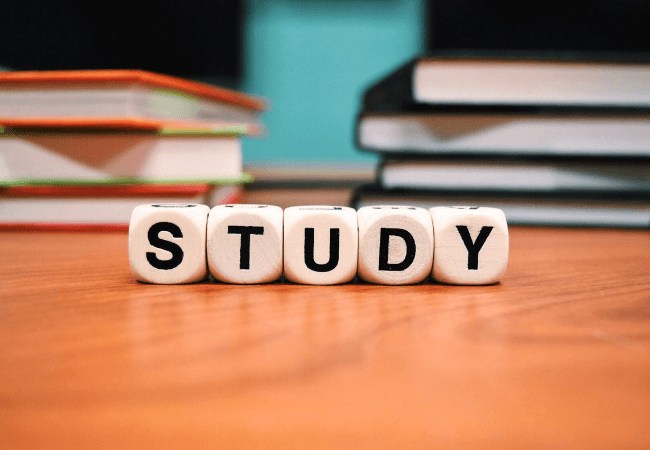
「ちょっと変わった自学ネタが知りたい」という方には、パソコンを使った自主学習がおすすめです。ゲーム感覚で取り組めるので、毎日無理なく続けることができますよ。大人になってからも役立つスキルが身につくので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
タイピングスキルが向上すると調べ学習が効率的に行えるだけでなく、将来の仕事にも役立つのでおすすめです。
タイピング練習は、無料サイトなどを活用して記録をとると良いでしょう。決められた時間で正確に入力する必要があるので、お子さんも集中して取り組めますよ。タイピングが速くなったり、手元を見ずに入力できるようになったりすると、自信もつきます。タイピングは遊び感覚で楽しく練習できるので、気軽に取り入れられる自学ネタです。
好きなテーマでランキングをつくることで、データを分析し視覚的に整理する力が身につきます。たとえば「人口が多い国ランキング」「〇〇の収穫量が多い都道府県ランキング」をパソコンを使ってまとめましょう。資料をつくる過程で自然と知識も身につけられますよ。
また友達にアンケートをとり「人気ゲームランキング」などのテーマで取り組めば、コミュニケーションの機会も増えるでしょう。ランキング作成は、情報整理力やプレゼン力を鍛える楽しい自学ネタです。
リストをつくる活動では、情報を効率的にまとめる力を鍛えられ、エクセルなどの操作を身につけることもできます。
たとえば「夏休みにやりたいことリスト」「読みたい本のリスト」などを作ってみましょう。表の中に優先順位や分類を加えると、実用的になります。さらに、色をつけたり、フィルタ機能を使ったりしてみるとよりわかりやすい表になるでしょう。リストや表をつくることは、楽しく取り組めるだけではなく、実生活にも役立つ自学ネタです。
プログラミングは小学校で必修化されたこともあり、これからの時代に不可欠なスキルといえます。ゲームや作品をつくることができるため、楽しみながら自学に取り入れられますよ。
小学生向けのプログラミング学習サイトを使って、無料で学習を始めてみるのも良いでしょう。簡単なアニメーションやゲームを作り、完成したら家族や友達に見せて共有するのも楽しいですよ。楽しみながら新しいスキルを身につけられるので、やりがいのある自学ネタです。

今回は、小6向けの「すぐ終わる自学ネタ」についてご紹介しました。自学のテーマに悩む子どもたちは多いもの。しかし適切な学習方法を見つけられないと、自学の時間が「ただの宿題の延長」になり、やる気や創造力を引き出すチャンスを逃してしまうかもしれません。
創造力を鍛える習い事として注目されているのが、プログラミングです。自分でゲームやアプリを作れるようになると、達成感や充実感も得られます。せっかく自由に学べる「自学」の時間、プログラミングにチャレンジしてみませんか。
「プロクラ」は子どもたちが大好きなマインクラフトの世界でプログラミングを学べるスクールです。「自主学習の時間を有意義に使いたい」と考えている保護者様は、ぜひこの機会に無料体験や資料請求からスタートしてみてくださいね。
COLUMN