


お子さんの習い事を選ぶ際、保護者様としては「長く続けてほしい」「将来社会に出たときに役立ててほしい」「周りもやっているから遅れを取りたくない」など、さまざまな思いを抱くものです。
お子さんの将来を思うからこそ、「この習い事がいいのでは」と提案したくなることもあるでしょう。
習い事を決めるときは、家族でしっかり話し合うことをおすすめします。お子さんが今何に興味を持っているのか、そして将来どんな大人になってほしいのか。
お互いが納得できる選択をすることが、長く続く秘訣です。
この記事では、後悔しない習い事の選び方のコツや、小学生のうちに伸ばしておきたい力、そしておすすめの習い事19選を紹介します。

せっかく始めた習い事なのに、「もう辞めたい」「思っていたのと違った」となってしまうのは避けたいですよね。
ここでは、小学生の習い事選びで失敗しないための5つの重要な視点をご紹介します。
まずは、お子さんの「やりたい!」「好き!」という気持ちを大切にすることです。
子どもたち自身が興味を持って始めたことは、モチベーションが高く、長続きしやすい傾向があります。好きなことに夢中になって取り組む時間は、自然と高い集中力を養うことにもつながるでしょう。
「ゲームが好き」「体を動かすのが好き」など、今の興味の延長線上に習い事がないか探してみるのがポイントです。
ただし、その興味が一時的なものではないか、保護者様がサポートできる範囲かどうかも見極める必要があります。お子さんの言葉だけに頼らず、生活スタイルも含めて検討しましょう。
「流行っているから」という理由だけで選ぶのではなく、将来社会に出たときにどのような力が必要になるかを想像し、そこから逆算して選ぶ視点も大切です。
例えば、「自分で問題を解決できる子になってほしい」「人前で堂々と意見を言えるようになってほしい」といった願いがあるなら、ただスキルを学ぶだけでなく、発表の機会がある習い事や、自分で考えるプロセスを重視する教室を選ぶと良いでしょう。
目的が明確になることで、習い事がよりお子さんの生きる力の育成につながります。

継続するためには、現実的な負担の確認が欠かせません。
習い事の費用は月謝だけでなく、入会金や教材費、ユニフォームや道具代、発表会費などがかかる場合もあります。高学年になるにつれて塾などの費用も増えるため、長期的な視点で無理がないか確認しましょう。
また、送迎の負担も重要です。自宅から通いやすい場所にあるか、送迎バスはあるかなどを確認し、保護者様の生活リズムを崩さずにサポートできる範囲で選ぶことが、家族全員の笑顔につながります。
お子さんの性格や、成長段階と習い事の相性も見極めましょう。
活発でエネルギーが有り余っている子にはスポーツ系、コツコツと積み上げることが得意な子にはピアノやプログラミングなど、個性を活かせる場所を選ぶと自己肯定感が育ちやすくなります。
また、カリキュラムの難易度も重要です。簡単すぎても飽きてしまいますし、難しすぎても自信を失ってしまいます。
「少し頑張ればできる」という適度なハードル設定がある教室なら、「できた!」という成功体験を積み重ねていけるでしょう。
もっとも重要なのが、「体験教室」への参加です。パンフレットやWebサイトの情報だけでは、実際の教室の空気感や、講師とお子さんの相性まではわかりません。
特にチェックしたいのは、講師が子どもたちをどのように指導しているか。一方的に教えるだけなのか、子どもたちの考えを引き出そうとしてくれているか。また、挨拶や感謝といった「礼儀」を大切にしているかどうかも、人格形成の面で重要なポイントです。
入会前に必ず体験に行き、お子さんが楽しそうにしているか、保護者様が安心してお任せできるかを確認しましょう。

習い事は、単なる技術の習得だけでなく、学校生活や将来の社会生活で必要となる「非認知能力(数値化しにくい力)」を育てる絶好の機会です。
ここでは、小学生のうちに伸ばしておきたい5つの生きる力について解説します。
小学生の時期は、他者との関わりの中で自分を認識し始める大切な時期です。この時期に「自分はできる」「自分は大切な存在だ」と思える自己肯定感を育むことは、一生の財産になります。
自己肯定感を高めるには、結果だけでなく、努力や過程を認めてもらう経験が不可欠です。
また、作品を発表したり、意見を伝えたりして「他者に認められる経験」を積むことも効果的です。自信がつくと、新しいことへの挑戦意欲も湧いてきます。
脳の発達が著しい小学生のうちに何かに没頭する経験を積むことで、集中力の土台が作られます。好きなことや興味のあることに夢中になっているとき、子どもたちの集中力は飛躍的に伸びています。
この集中力は、将来の受験勉強や、仕事で複雑な課題に取り組む際の基礎です。
机に向かう勉強だけでなく、スポーツや創作活動など、時間を忘れて取り組める環境を用意してあげましょう。
AI技術が進化するこれからの時代、ゼロから新しい価値を生み出す「創造力」はますます重要になります。
好奇心旺盛な小学生の時期に、正解のない問いに対して自分なりの答えを出したり、自由な発想で形にしたりする経験が創造力を養うことが大切です。
絵画や工作、プログラミングなど、自分の頭の中にあるイメージを具現化する習い事は、創造力を伸ばすのに最適。
「どうすればもっと面白くなるかな?」と試行錯誤するプロセスそのものが、学びになるでしょう。

物事を筋道立てて考え、解決へと導く「論理的思考力」は、社会で活躍するために必須のスキルです。
2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されたのも、この力を養うためです。
「AをするためにはBが必要で、もしCになったらDをする」といった思考の組み立ては、算数や理科だけでなく、日常生活の問題解決や、相手にわかりやすく伝えるコミュニケーションの場面でも役立ちます。
学校以外のコミュニティに属することで、多様な人との関わり方を学びます。
チームスポーツやグループレッスンのある習い事では、役割分担や譲り合い、力を合わせて目標を達成する経験ができるでしょう。
また、習い事の場では「始まりと終わりの挨拶」や「道具を大切にする」「送迎してくれる親への感謝」といった、人として大切なマナーを学ぶこともできます。
これらは将来、社会人として信頼されるための土台となります。

ここからは、将来役に立つスキルが身につけられる、小学生におすすめの習い事をご紹介します。
ジャンル別に特徴をまとめましたので、お子さんの興味と「伸ばしたい力」を照らし合わせながらご覧ください。
小学校での必修化以降、人気が急上昇しているのがプログラミング教室です。単にコードを書く技術を学ぶだけでなく、「論理的思考力」「問題解決力」「創造力」を総合的に鍛えられるのが最大の特徴です。
プログラミングでは、自分が意図した動きを実現するために順序立てて命令を組みます。うまくいかないときは「なぜ動かないのか?」を分析し、修正して再挑戦。
このトライ&エラーの繰り返しが、粘り強く考える力と、失敗を恐れずに挑戦する心を育てます。
また、最近では「マインクラフト」などの人気ゲームの世界で学べる教室も増えており、勉強という意識を持たずに、遊びの延長で熱中できるのも魅力です。
作成した作品を発表する機会がある教室なら、プレゼンテーション能力や自己表現力も同時に身につきます。IT社会を生き抜くための必須スキルとして、男女問わずおすすめしたい習い事です。
あわせて読みたい ▼ 子どもがプログラミング学習をするメリットとは
グローバル化が進む現代において、英語は「勉強」ではなく「コミュニケーションツール」です。
耳のいい小学生のうちから英語特有のリズムや発音に触れることで、英語への抵抗感をなくし、素地を作ることができます。
異文化に触れることで視野が広がり、多様な価値観を受け入れる柔軟性も育つでしょう。
学校の授業の予習・復習や、中学受験を見据えた学力向上を目的としています。
決まった時間に机に向かうことで学習習慣が身につき、計画的に物事を進める力が養われます。「わかった!」という喜びは学習意欲を高め、自ら学ぶ姿勢へとつながるでしょう。
計算スピードと、正確性が身につく伝統的な習い事です。
頭の中でそろばんを弾く「暗算」のトレーニングは、右脳を活性化させ、直感力や集中力を高めると言われています。
数字に強くなることは、理数系科目の基礎力向上にも直結します。
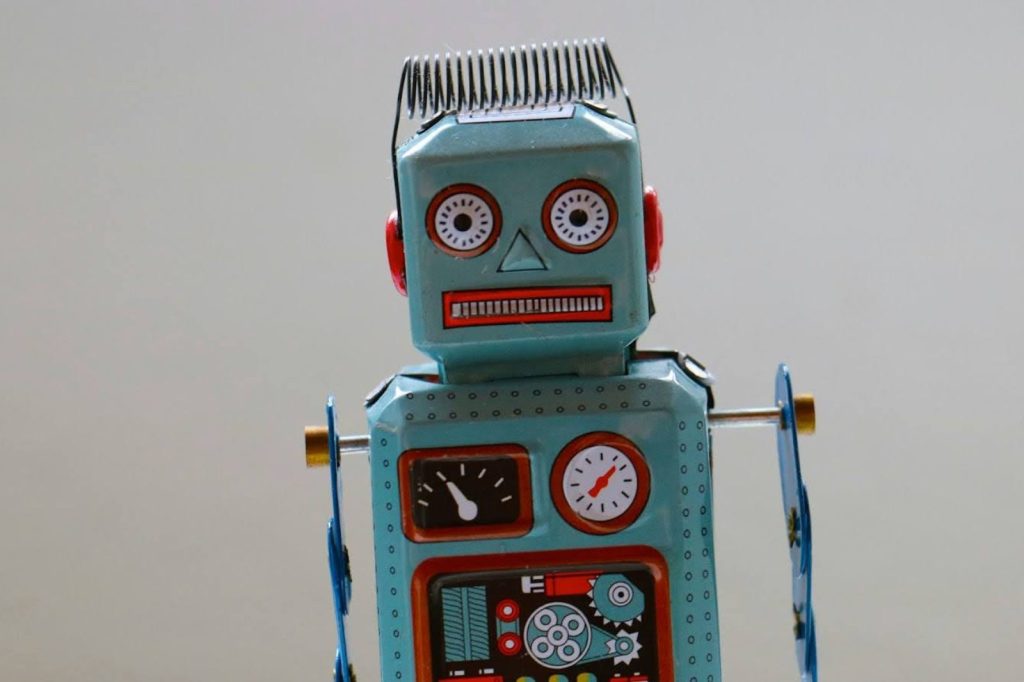
ブロックやパーツを組み立ててロボットを作り、それをプログラムで動かします。
「空間認識能力」と「プログラミング的思考」を同時に養えるのが強みです。
自分の手で作ったものが動く感動は大きく、ものづくりへの関心や、理科・科学への興味を引き出します。
「なぜ空は青いの?」「どうして水は凍るの?」といった身近な疑問を、実験や観察を通して解明していきます。
仮説を立て、検証し、結果を考察するという科学的なアプローチを学ぶことで、論理的な思考力や探究心が深まります。
長年、小学生の習い事ランキングで上位に入る定番の習い事です。
全身運動により基礎体力が向上し、心肺機能も強くなります。進級テストという明確な目標があるため、目標達成に向けて努力するプロセスを学びやすいのもメリットです。
中学校でのダンス必修化もあり、人気が高まっています。
リズム感や体力だけでなく、鏡を見て自分を表現することで自己肯定感や表現力が磨かれます。チームで振付を合わせる過程では、協調性も身につくでしょう。

サッカー・フットサルは、チームプレーの代表格です。
走り回るための体力や瞬発力はもちろん、仲間と連携してゴールを目指すことで、コミュニケーション能力や社会性が育まれます。
試合を通して、勝つ喜びや負ける悔しさを経験し、精神的にもたくましくなります。
マット運動や鉄棒、跳び箱などを通して、柔軟性やバランス感覚といった運動の基礎能力を養います。
すべてのスポーツの土台となる身体能力が身につくため、低学年から始める習い事としても人気です。
投げる、打つ、走るという動作に加え、戦術理解などの頭脳プレーも求められます。
道具を大切にする心や、挨拶・礼儀を重んじる指導が多く、規律正しい生活習慣が身につくことも期待できます。
「礼に始まり礼に終わる」と言われるように、心身の鍛錬と礼儀作法を重視します。
技の習得だけでなく、相手を敬う心や、己に打ち勝つ精神力が養われます。いざという時に身を守る術としても役立つでしょう。
壁にある突起(ホールド)を使って登るスポーツです。
「どのルートを通れば登れるか」を考えるパズル的な要素があり、思考力と判断力が鍛えられます。全身の筋肉をバランスよく使い、体幹も強くなります。

フィギュアスケートは、スポーツとしての運動能力と、芸術としての表現力の両方が求められます。
氷の上でバランスを取ることで体幹が鍛えられ、音楽に合わせて演技をすることで感性が磨かれます。人前で表現する度胸も身につくでしょう。
指先を複雑に動かすピアノは、脳の発達に良い影響を与えると言われています。
楽譜を読むことで先読みする力がつき、毎日の練習を継続することでコツコツ努力する習慣(グリット=やり抜く力)が育まれます。
正しい姿勢と美しい文字は、一生の財産です。静寂の中で文字と向き合う時間は、高い集中力を養います。
デジタル時代だからこそ、丁寧な手書きの文字は相手に好印象を与え、信頼につながります。
絵画教室は、自分の世界観を色や形で表現する楽しさを学びます。
正解のない創作活動は、自由な発想や独創性を伸ばします。観察力が鋭くなり、物事を多角的に見る視点が養われるでしょう。
近年、藤井聡太さんの活躍などで注目されています。
数手先まで読む論理的思考力、局面を判断する大局観、そして長時間考え続ける集中力が鍛えられます。負けを認め(投了)、振り返る(感想戦)文化は、素直な心を育てます。
合唱は個人の技術だけでなく、周りの声を聴き、声を合わせる協調性が不可欠です。
歌詞の意味を考え、感情を込めて歌うことで感受性が豊かになります。仲間と一つの音楽を作り上げる達成感は格別です。

ここからは、習い事を始めるときや辞めるときの注意点を解説します。
大切なのは、常にお子さんと対話を重ねることです。せっかくの習い事ですから、お子さんが楽しく、充実した時間を過ごしながら、長く続けられるようにしていきましょう。
保護者様としては、「せっかくやるなら上達してほしい」「将来のために続けてほしい」と期待してしまうもの。
しかし、その期待がプレッシャーとなり、お子さんの負担になってしまっては本末転倒です。
習い事の主役は、あくまでお子さんです。始める際は「これがやりたい!」という興味を尊重し、通っている間は結果よりも「楽しめているか」「頑張っているか」を見守ってあげましょう。
無理強いは、学ぶこと自体への意欲を削いでしまう可能性があります。
「〇〇ちゃんはもうあんなことができるのに」「どうしてあなたは進むのが遅いの?」といった言葉は、絶対にNGです。上達のスピードや得意・不得意は一人ひとり異なります。
他者との比較ではなく、「先月よりここができるようになったね」「練習を続けていてえらいね」と、過去のお子さんと比較して成長を認める声かけを心がけましょう。
保護者様に認められることが、お子さんの自信とやる気の源になります。
「一度始めたら辞めてはいけない(継続は力なり)」と考える方も多いですが、どうしても合わない場合は、無理せず辞める勇気を持つことも大切です。
講師との相性が悪かったり、教室の雰囲気が合わなかったりすることは、誰にでもあります。
辞めることは逃げではなく、より自分に合う場所を探すための前向きな選択です。「なぜ辞めたいのか」「次はどんなことをしてみたいか」を親子でしっかり話し合い、次のステップにつなげていきましょう。

小学生のうちは、ただ楽しいだけでなく、将来社会に出たときに役立つ力を身につけておくと、お子さんの可能性が大きく広がります。
とくに、AI技術が発展し変化の激しいこれからの時代には、「自ら考え、答えを導き出し、それを他者に伝える力」が求められます。
プログラミング教室「プロクラ」では、単なるプログラミング技術の習得にとどまらず、論理的思考力や問題解決力、そして創造力やコミュニケーション力といった「生きる力」を総合的に育みます。
「ゲームばかりしているのが心配…」という保護者様も、その「好き」を学びに変えるチャンス。 プロクラでは、少人数制で一人ひとりに寄り添った指導を行っています。また、授業では親御様への感謝を伝える時間もあり、心の成長も大切にしています。
お子さんが目を輝かせて学ぶ姿を、ぜひ一度体験しに来てください。 まずは無料体験教室で、マインクラフトの世界でのプログラミング学習を体験してみませんか?
COLUMN