


最近、テレビや新聞、学校の授業などで「SDGs」という言葉を耳にする機会が増えていませんか。色とりどりの17個のマークがセットになったロゴを見たことがある方も多いでしょう。しかし「SDGsとは何なのか」「なぜ今こんなに注目されているのか」について、詳しく知っている小学生は少ないかもしれません。SDGsとは、世界中の人々がより良い未来を作るために決めた大切な約束のことです。地球上に住むすべての人々が幸せに暮らせるよう、みんなで力を合わせて取り組むという目標を掲げています。今回は、このSDGsについて小学生にもわかりやすく解説していきます。みなさんも身近なところからSDGsに取り組んで、未来の地球を守る仲間になりませんか?

SDGsとは、世界中の国々が力を合わせて取り組む17の大きな目標のことです。地球上のすべての人が幸せに暮らせる世界を作るために、2030年までに達成しようと決めた約束です。
SDGsとは「Sustainable Development Goals」という英語の頭文字を取った略称のことで、日本語では「持続可能な開発目標」と呼ばれています。「持続可能」とは、今だけでなく未来の人々も同じように豊かに暮らせることを意味します。つまり、今の私たちが便利で快適な生活を送りながらも、将来の子どもたちや孫たちも同じように良い環境で暮らせるようにすることが大切だという考え方です。
SDGsは、2015年9月に国連で採択された国際的な目標です。世界193の国と地域が参加して、2030年までに達成することを約束しました。これは、世界中の国々が同じ方向を向いて協力することを決めた歴史的な出来事。
それまでも似たような取り組みはありましたが、SDGsとは特に「誰一人取り残さない」ことを大切にしている点が特徴です。つまり、お金持ちの人だけでなく、貧しい人々も含めて、すべての人が幸せになれる世界を目指しています。

私たちが住む地球では、今さまざまな問題が生じています。世界には十分な食べ物がないために苦しんでいる人々がいたり、きれいな水を飲むことができない地域があったりします。また、地球温暖化によって異常気象や自然災害が増え、戦争や差別によって平和に暮らせない人々もいるのです。これらの問題は一つの国だけでは解決できません。
SDGsとは、このような世界中の課題を解決するために生まれた目標です。未来の地球がもっと住みにくい場所になってしまう前に、世界中の人々が協力して、持続可能な社会を作る必要があります。SDGsとは、私たち一人ひとりの行動が地球の未来を左右する大切な取り組みなのです。

SDGsとは、17の具体的な目標で構成されています。それぞれに色分けされたマークがあり、どの目標も同じように重要です。貧困や飢餓の解決から、環境保護、平和の実現まで幅広い内容が含まれています。
世界中の極度の貧困を終わらせることを目指した目標です。貧困とは、食べ物や住む場所、教育を受ける機会などが十分でない状態を指します。
現在、世界には1日200円以下で生活している人々がいます。貧しい家庭の子どもたちは学校に通うことができず、病気になっても適切な治療を受けられない人々も多く存在するのです。そのためSDGsでは、すべての人が基本的な生活を送れるようにすることを大切にしています。
2030年までに世界から飢餓をなくし、すべての人が栄養のある食べ物を安定して食べられるようにすることを目指した目標です。世界では約8億人の人々が十分な食べ物を得ることができていません。
飢餓の主な原因は気候変動による農作物の不作、戦争や紛争、貧困などが挙げられます。食べ物は十分に生産されているにも関わらず、運搬や保存の問題で無駄になってしまうケースも多くあるのです。
年齢や住んでいる場所に関係なく、すべての人が健康で長生きできる社会を作ることを目指した目標です。
世界では、基本的な医療を受けることができずに命を落とす人々がまだまだたくさんいます。特に妊婦や子どもの死亡率を下げることが急務とされており、感染症や生活習慣病の予防、精神的な健康の向上も重要な課題です。
健康な人々が増えることで、社会全体がより活発となり、経済も発展し、医療費の負担も軽くなるでしょう。
2030年までにすべての子どもたちが質の高い教育を受けられるようにすることを目指した目標です。教育は、すべての子どもたちが持つ基本的な権利です。
しかし、世界には学校に通えない子どもたちが約2億6000万人もいます。教育は貧困から抜け出すための重要な手段です。教育を受けることで、子どもたちの将来の可能性は大きく広がります。
教育を受けた人々が増えると、社会全体の知識や技術が向上し、より良い世界を作ることができるのです。
性別によって差別されることなく、男性も女性も同じように機会や権利を持てる社会を作ることを目指した目標です。
現在でも、女性というだけで教育を受けられなかったり、働く機会が制限されたりする地域があります。政治や経済の分野で意思決定に参加する女性の割合も少ない状況が続いているのです。
男性と女性が平等になることで、より多くの人々のさまざまなアイデアや能力を活用できるようになり、社会全体がより豊かで発展的になるでしょう。
2030年までにすべての人が安全な水を利用でき、適切な衛生設備を使えるようにすることを目指した目標です。
世界には安全な水を飲むことができない人々が約20億人も存在します。汚れた水を飲むことで病気になったり、女性や子どもたちが水くみのために長時間歩かなければならなかったりする地域があるのです。
きれいな水と適切なトイレがあることで、病気を防ぎ、女性も子どもたちも勉強や仕事に時間を使うことができるでしょう。
すべての人が安価で安全なエネルギーを利用できるようにし、環境に優しいクリーンエネルギーの利用を拡大することを目指した目標です。
世界には電気を使えない人々が約7億6000万人もいます。従来の化石燃料は地球温暖化の原因となるため、太陽光や風力など再生可能エネルギーへの転換が重要です。
クリーンで安価なエネルギーが普及することで、地球環境を守りながら経済発展を続けることができるのです。
すべての人が安全で公正な労働環境で働き、経済的に豊かになれる社会を作ることを目指した目標です。
世界には、危険な環境で働かされている人々や、十分な給料をもらえない人々がたくさんいます。特に子どもたちが学校に行かずに働かされている児童労働は深刻な問題です。
すべての人が働きがいのある仕事に就けるようになれば、社会全体が豊かになります。技術の進歩と公正な労働環境が組み合わされることで、持続可能な経済成長が実現できるのです。
インフラを整備し、持続可能な産業化を促進するとともに、技術革新を推進することを目指した目標です。産業の基盤とは、工場や道路、インターネットなど社会を支えるインフラのことを指します。
世界には、まだ十分なインフラが整備されていない地域があるため、人々の生活が不便になったり、経済活動が制限されたりしています。産業の基盤が整い、技術革新が進むことで、より効率的で環境に優しい産業が生まれ、多くの雇用機会も創出されるでしょう。
国内や国家間の格差を減らし、すべての人が平等な機会を得られる社会を作ることを目指した目標です。現在の世界では、お金持ちの人はより豊かになり、貧しい人はますます貧しくなるという格差が広がっています。
また、先進国と発展途上国の間にも大きな差があり、生まれた場所によって受けられる教育や医療のレベルが大きく異なるのが現状です。この不平等をなくすことで、すべての人が自分の能力を発揮し、社会に貢献できる機会を得ることができるでしょう。
すべての人にとって安全で快適な都市や住環境を作り、持続可能な発展を実現することを目指した目標です。多くの都市では大気汚染や交通渋滞、住宅不足などの問題が深刻化し、自然災害に対して脆弱な地域も多く、安全に住み続けることが困難な場所もあります。
持続可能なまちづくりには、公共交通機関の整備、緑地の確保、リサイクルシステムの構築などが必要です。すべての人が安心して住み続けられるまちができれば、経済も環境も健全に発展していくでしょう。
持続可能な方法でものを生産し、消費することを目指した目標です。現在の社会では、大量生産・大量消費・大量廃棄が当たり前になっていて、地球の資源が枯渇したり、環境汚染が進んだりする原因となっています。
企業には環境に配慮した製品を作る責任があり、消費者には必要なものだけを買い、長く大切に使う責任があります。みんなが責任を持って行動することで、限りある地球の資源を未来の世代にも残すことができるでしょう。
地球温暖化による気候変動に対して緊急の行動を取ることを目指した目標です。地球の気温は年々上昇していて、その影響で異常気象や自然災害が増加し、多くの人々の生活に深刻な被害をもたらしています。海面上昇により沈んでしまう島国もあり、動植物の生息地も失われつつあります。
すべての国が協力して、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を減らし、再生可能エネルギーの利用を拡大することで、気候変動の進行を止めることができるでしょう。
海洋と海洋資源を持続可能な方法で利用し、保全することを目指した目標です。海は地球表面の70%を占め、多くの生き物の住みかとなっているほか、気候を調整する重要な役割も果たしています。しかし、プラスチックごみによる海洋汚染や過度な漁業により、海の生態系が破壊されている現状です。
また海水温の上昇によりサンゴ礁が死滅し、多くの海洋生物が絶滅の危機に瀕しています。海を守ることは、私たちの生活を支える酸素の供給や食料の確保にも直結しているのです。
森林や砂漠、山地などの陸上生態系を保護し、持続可能に利用することを目指した目標です。森林は二酸化炭素を吸収し、酸素を作り出す地球の肺とも呼ばれていますが、毎年大量の森林が失われています。また、土地の劣化や砂漠化により、農業ができなくなる地域も増えているのが現状です。
多くの動植物が絶滅の危機に瀕していて、生物多様性の損失も深刻な問題となっています。陸上の自然環境を守ることは、私たちの食料や水の確保、気候の安定にも欠かせないのです。
平和で包括的な社会を作り、すべての人が司法制度にアクセスできるようにすることを目指した目標です。世界では今も戦争や紛争が続いている地域があり、多くの人々が平和に暮らすことができずにいます。
また、汚職や不正が横行している国では、公正な裁判を受けることが困難で、基本的人権が守られていない場合もあります。すべての人が平和で安全な環境で暮らし、公正な扱いを受けられる社会を築くことで、持続可能な発展の基盤が整うはずなのです。
SDGsの16の目標を達成するために、世界中の国や組織、個人が協力して取り組むことを目指した目標です。地球規模の課題は一つの国だけでは解決することができないため、すべての関係者が力を合わせることが不可欠となっています。
政府だけでなく、企業や市民団体、学校、そして私たち一人ひとりが役割を果たす必要があります。この目標は、他の16の目標をつなぐ重要な役割を担っていて、みんなで協力することでSDGsの達成が可能になるのです。

SDGsの17の目標を達成するためには、世界中の人々一人ひとりの行動が重要です。「今自分たちには何ができるのか?」を考えながら、お子さんと一緒に取り組めることから始めてみましょう。
SDGsについて学ぶことは、SDGsの達成に向けた行動の第一歩です。17の目標がなぜ必要なのか、どのような問題を解決しようとしているのかを理解することで、家庭でできることが見えてきます。
お子さんと一緒にSDGsについて調べたり、ニュースで世界の出来事について話し合ったりしてみましょう。図書館でSDGsに関する本を借りてお子さんと一緒に読んだり、学校での学習内容を家庭でも話題にしたりすることで、理解を深めることができます。
世界では多くの人々が飢餓に苦しんでいることを、お子さんと一緒に学ぶことから始めましょう。家庭では、食事の際に「いただきます」「ごちそうさま」としっかり挨拶し、食べ物への感謝の気持ちを育むことが大切です。
お子さんには出された分をできるだけ残さず食べるよう声をかけ、好き嫌いを減らしていく働きかけも必要です。また、一緒に料理することで、食べ物の大切さを実感してもらうことができるでしょう。
世界には安全な水を飲めない人々がたくさんいることを、お子さんにわかりやすく説明してあげましょう。歯磨きや手洗いの際に、お子さんと一緒に「水を出しっぱなしにしない」ことを実践し、なぜ大切なのかを教えることが重要です。
電気についても、電気を消すことを習慣化し、なぜ省エネルギーが大切なのかを説明してあげましょう。夏や冬のエアコンの設定温度も、お子さんと一緒に適切な温度を確認することで、環境への意識を育むことができるはずです。
正しいごみの分別を、お子さんと一緒に楽しく学ぶことから始めましょう。自治体のルールに従って、お子さんと一緒にペットボトルや缶、紙類などを分別し、なぜリサイクルが大切なのかを説明してあげることが重要です。
お子さんには、ごみを捨てる前に「もう一度使えないかな」と一緒に考える習慣をつけてもらいましょう。また、家族でごみ拾いのボランティア活動に参加することで、お子さんに環境保護の大切さを実感してもらうのも効果的です。
思いやりの心を育てるために、お子さんと一緒に身近な人を助ける経験を積むことが大切です。近所のお年寄りに挨拶したり、重い荷物を持っている人を見かけたら一緒に声をかけたりすることから始められます。
また、家族で募金活動に参加したり、使わなくなったおもちゃや文房具を一緒に整理して寄付したりすることで、世界の困っている人々への支援について学ぶことができます。小さな親切の積み重ねが大きな力になることを、お子さんと一緒に実感してみましょう。
ものを大切に使うことの重要性を、お子さんと一緒に実践しながら学びましょう。お子さんの服や靴が小さくなったときは、兄弟や友人に譲ったり、リサイクルショップを活用したりすることができます。
また、お子さんと一緒に工作をする際は、空き箱やペットボトルなどの廃材を材料として活用することで、創造性を育みながらリサイクルの大切さを学べるでしょう。新しいものを買う前に、お子さんと「本当に必要かな」と一緒に考える習慣をつけることも重要です。
自然環境を守ることの大切さを、お子さんと一緒に体験しながら学びましょう。自宅やベランダでお子さんと一緒にガーデニングを楽しんだり、植物や虫を観察したりすることで、自然への興味と愛着を育むことができます。
公園や山、海に遊びに行ったときは、お子さんと一緒に生き物を探したり、季節の変化を感じたりする時間を作ることも効果的です。また、環境に優しい商品を選ぶことで、地球に優しいものを選択する意識を育てることもできるでしょう。
性別に関係なくすべての人と平等に接することの大切さを、お子さんと一緒に実践しましょう。家庭では「男の子だから」「女の子だから」という言葉を使わず、お子さん一人ひとりの個性を大切にすることが重要です。
服装や物の色、デザインなども、たとえそれが性別のイメージと違うものであっても、尊重してあげることが大切なのです。また、絵本やアニメを一緒に見る際にも、ジェンダー平等の視点で多様な価値観について話し合うのも良いでしょう。
環境を守るための行動を、お子さんと一緒に習慣化しましょう。家族でお買い物に行く際は、お子さんと一緒にマイバッグを持参し、なぜレジ袋を減らすことが大切なのかを説明してあげることが重要です。
また、親子でマイボトルを持参したり、お子さんと一緒に「包装は必要かな」と考えたりすることも効果的です。買い物を通じて、お子さんと一緒に地球に優しい選択習慣を身につけることで、環境意識を自然に育むことができます。
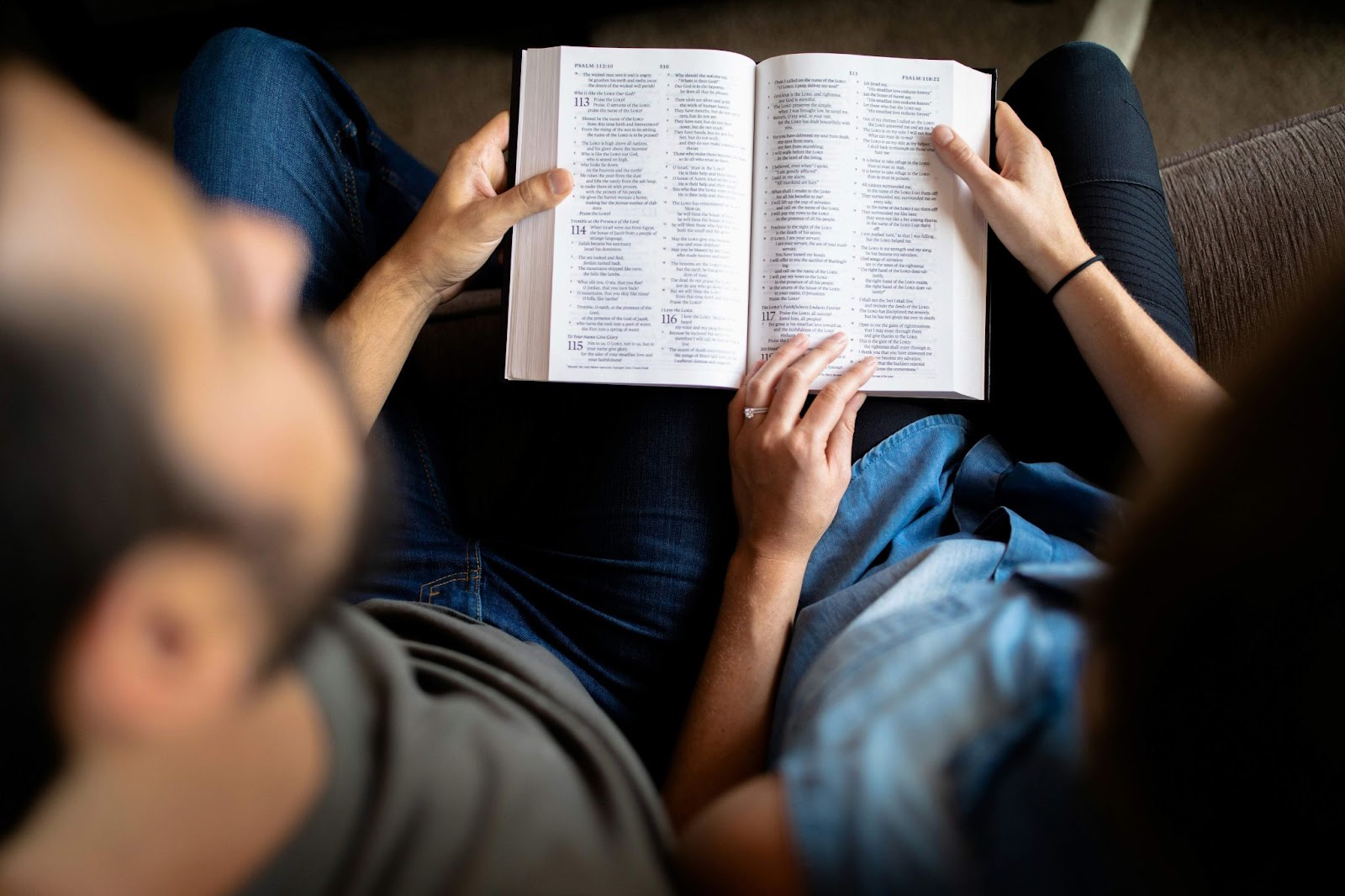
SDGsへの理解をより深めるためには、本を読んだりイベントに参加したりするなど、さまざまな方法で情報に触れることが大切です。お子さんの年齢や興味に合わせて、楽しく学べる方法を選んでみましょう。
SDGsについて詳しく学ぶには、書籍を活用することが効果的です。小学生向けのSDGs解説書や絵本が数多く出版されているので、お子さんの年齢に適したものを選んで一緒に読んでみましょう。
漫画形式やイラストが豊富な本なら、お子さんも楽しみながら学習できるはずです。また、保護者様も一緒に読むことで、理解を共有することができ、読んだ内容について話し合うことができるため、学びをより定着させることができるでしょう。
学校教育でもSDGsは重要なテーマとして扱われているため、お子さんに学校での学習内容について聞いてみましょう。授業で学んだことを家庭で話題にすることで、お子さんの理解がより深まります。
また、学校におけるSDGsに関する取り組みや活動を知ることで、家庭でも同様の取り組みを実践できるかもしれません。学校と家庭が連携してSDGs教育を進めることで、お子さんにとってより効果的な学習環境を整えることができるでしょう。
SDGsについて家族で話し合う時間を定期的に作ることが、理解を深める最も身近な方法です。夕食の時間や休日のひとときを使って「今日はどんなSDGsに関する行動ができたかな」「明日はどんなことを心がけようか」と会話してみましょう。
お子さんが学校で学んだことや、テレビで見たニュースについて家族で意見交換することも効果的です。お子さんの意見や疑問を大切にしながら、一緒に考える姿勢を持ちましょう。
地域で開催されるSDGs関連のイベントやワークショップに家族で参加することで、より実践的に学習できます。自治体や企業、NPO団体などが主催するSDGs体験イベントでは、楽しみながら学べるよう工夫されているため、お子さんも興味を持ちやすいはずです。
また、博物館や科学館でもSDGsに関するイベントがあるので、情報をチェックしてみましょう。参加後は家族で、学んだことを日常生活に生かす方法を考えてみる時間を作ると良いでしょう。

SDGsという言葉を初めて聞いたとき、自分とは関連が薄いと感じた方も多いのではないでしょうか。しかし、SDGsの目標は私たちの日常生活と密接に関わっています。食べ物を残さないことも、電気を大切に使うことも、友達と仲良くすることも、すべてSDGsの目標達成につながる行動なのです。
大切なのは、まず「知りたい」「やってみたい」という気持ちを持つことです。小さな関心から大きな学びが生まれ、それが未来をより良くする力となります。完璧を目指さず、できることから少しずつ始めることで、SDGsは決して遠い存在ではなく、私たちの身近にある取り組みだということが実感できるはずです。

SDGsについて学ぶなかで、お子さんが「こんな問題を解決するにはどうしたらいいんだろう」「もっと便利で環境に優しいものを作りたい」と考えるようになったら、それは素晴らしい成長の証。そんなお子さんの探究心や創造力をさらに伸ばしたいとお考えなら、プログラミング教育がおすすめです。
プロクラでは、マインクラフトの世界を通じて楽しくプログラミングを学びながら、論理的思考力や問題解決能力を身につけることができます。子どもたちの「やってみたい」という気持ちを大切にし、一人ひとりの個性や発想を伸ばせるよう教育しています。プロクラで培った創造性と論理的思考が、お子さんの将来の可能性を大きく広げてくれるはずです。
COLUMN