
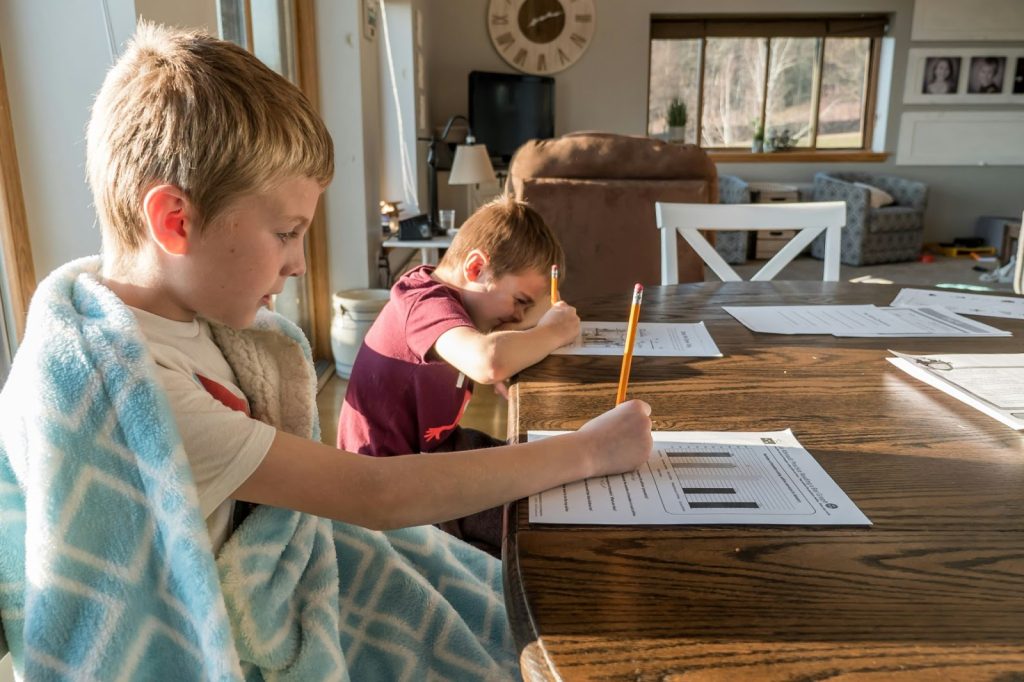

現代社会ではデジタル化が急速に進み、私たちの生活や仕事のあり方が大きく変化しています。スマートフォンやタブレット、パソコンなどのデジタル機器が普及し、買い物や銀行、行政手続きまでオンラインで完結できるようになりました。このデジタル化の波は教育分野にも広がり、学校での授業や家庭学習にもデジタルツールが活用されています。
便利になった一方で、子どもたちを取り巻くデジタル環境には注意が必要です。お子さんがデジタル社会で健やかに成長するためには、デジタル化のメリットを最大限に生かしながら、デメリットに適切に対応することが大切です。デジタル化社会の現状とその影響、そして親子で取り組める対策について見ていきましょう

デジタル化が進む現代社会では、生活や仕事、教育などさまざまな場面で変化が生じています。情報共有やコミュニケーションの円滑化、オンライン教育の普及など、デジタル化がもたらす効果は、社会全体の可能性を広げていくでしょう。
デジタル化によって多くの作業が自動化され、生産性が大幅に向上しています。たとえば、かつては手作業だった計算や文書作成、データ整理などがデジタルツールによって素早く正確に処理できるようになりました。企業だけでなく、家庭や学校でもデジタル技術の活用によって、時間や労力を節約できるメリットがあります。子どもたちにとっても、デジタル機器を適切に活用することで、学習効率が高まるでしょう。
長期的に見て、デジタル化によるメリットはコスト削減につながることです。紙の資料や保管スペースが不要になるだけでなく、移動時間や交通費の節約にもつながります。家庭においても、オンラインでの手続きが増えたことで、窓口に出向く手間や時間が省けるようになりました。
また、オンライン会議システムの普及により、出張費や交通費が削減され、ビジネスだけでなく学校の授業などでも時間と費用の節約につながっています。
デジタル化によって、情報の管理や共有が格段に円滑となりました。クラウドサービスの普及により、大量の情報を安全に保存し、必要なときにどこからでもアクセスできるようになっています。家庭内でも、家族の予定や写真、重要書類などをデジタルで共有・管理することで、情報の整理が容易になったのです。学校と家庭の連携もデジタル化が進み、お子さんの学習状況や学校からのお知らせをタイムリーに把握できるメリットがあります。
デジタル化の大きなメリットとして、コミュニケーションの効率化が挙げられます。メールやチャット、ビデオ通話などのツールにより、時間や場所を問わずコミュニケーションがとれるようになりました。家族や友人との連絡がスムーズになっただけでなく、学校と保護者様との連絡もデジタル化が進み、より迅速で効率的な情報共有が可能となっています。お子さんにとっても、友達との交流や情報交換の幅が広がるのがメリットでしょう。
デジタル化は世界をつなぎ、グローバル化を促進するメリットがあります。言語の壁を越えた翻訳ツールや、世界中の情報にアクセスできるインターネットの普及により、地理的な制約なく知識や文化を学べるようになったのです。お子さんにとっても、世界の多様な文化や価値観に触れる機会が増え、グローバルな視野を育むきっかけとなっています。デジタル技術を通じて、世界中の人々とつながる可能性が広がっているのです。
デジタル化によって、働き方の選択肢が大きく広がりました。テレワークやフレックスタイム制の導入が進み、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方が可能となっています。多様な働き方のメリットは、子育て中の保護者様にとって特に大きく、仕事と家庭の両立がしやすくなったことです。また、お子さんの将来においても、デジタルスキルを身につけることで、多様な働き方の選択肢が広がる可能性があります。変化する社会で活躍するために、デジタル技術への理解は必要なのです。
デジタル化により、教育の機会が大きく広がっています。地理的な制約を超え、遠隔地にいる優れた講師から学べるようになりました。また、デジタル教材はお子さんの理解度や進度に合わせて内容を調整できるため、一人ひとりに合った学びが可能です。さらに感染症の流行時など緊急時にも学習を継続できる環境が整い、教育の安定性も高まりました。デジタル化はお子さんの学習の選択肢を増やし、将来必要なスキルを身につける場を広げています。

デジタル化には便利さや効率性の一方で、注意すべき側面もあります。情報過多やセキュリティ、デジタル依存、対面コミュニケーションの減少、導入コストなど、デジタル社会で注意すべきデメリットについて見ていきましょう。
デジタル化には、膨大な情報にも簡単にアクセスできるメリットと、情報量が多すぎることで混乱を招くデメリットがあります。特に子どもたちは、正しい情報と間違った情報を見分ける力が十分に育っていないため、何を信じればよいか迷うことも。また、次々と新しい情報が流れてくることで、集中力の低下や思考がまとまらなくなる可能性もあります。情報の質を見極め、必要な情報を選択する力を養うことが重要です。
デジタル化に伴い、個人情報の漏洩やサイバー攻撃などセキュリティリスクが高まっています。特に子どもたちは、危険性を十分に理解せずにオンラインで個人情報を共有してしまうケースも。また、不適切なコンテンツへのアクセスや、知らない人とのオンラインでのやり取りなど、デジタル空間特有の危険も存在しているのです。家庭でのセキュリティ対策やリテラシー教育が重要となり、保護者様の見守りと指導が欠かせません。
デジタル機器やサービスの便利さから、過度に依存してしまうリスクも無視できません。スマートフォンやゲーム、SNSなどへの依存は、子どもたちの健全な発達や生活リズムに悪影響を及ぼす可能性も。長時間のスクリーン利用による視力低下や睡眠障害、運動不足なども懸念点です。また、デジタル機器に頼りすぎることで、基本的な計算力や記憶力の低下、実体験を通じた学びの機会が減少するなど、認知や学習面での影響も指摘されています。
デジタルコミュニケーションの普及により、対面でのやり取りが減少するデメリットがあります。表情や声のトーン、身振り手振りを含めた豊かなコミュニケーションを経験することは、社会性や共感能力を育む上で重要です。テキストベースのコミュニケーションでは感情の機微が伝わりにくく、誤解が生じることも。また、デジタル空間でのコミュニケーションに偏ることで、リアルな人間関係構築の機会が減少し、社会的スキルの発達に影響する可能性もあるでしょう。
デジタル化を進めるには、初期投資や継続的なコストが必要です。家庭でも、デジタル機器の購入や通信費、サブスクリプションサービスの利用料などさまざまな経済的負担が生じるほか、機器の更新や新しいソフトウェアの導入など、技術の進化に合わせた追加コストも発生します。お子さんの年齢に応じた適切な機器選びや、家族で共有できるサービスの検討など、長期的な視点でコストを抑える工夫が必要になるでしょう。

デジタル化が進む現代社会では、メリットとデメリット以外にもさまざまな問題があります。デジタル機器を持つ人と持たない人、使いこなせる人とそうでない人の間の「情報格差」が広がり、教育や就職の機会に差が生まれています。また、個人情報の収集と利用に関するプライバシーの問題も懸念点でしょう。
子どもたちの間では、SNS上でのいじめや個人情報の流出トラブルが増加しています。また、自分の好みに合った情報ばかりに触れることで、異なる意見や考え方を知る機会が減り、視野が狭くなることも。
急速に進化し続けるデジタル社会に対して柔軟に対応し、情報を正しく判断する力を身につけることが重要なのです。

デジタル化が進む社会で子どもたちが健やかに成長するためには、家庭での取り組みが重要です。デジタルリテラシーを身につけ、ルールを決め、オフラインの時間とのバランスを取りながら、デジタルとの付き合い方を身につけていきましょう。
情報化社会を生きていくには、デジタル機器の操作方法だけでなく、情報の信頼性を見極める力やオンライン上でのマナーなど、総合的なデジタルリテラシーが重要です。たとえば、ニュースを見るときに「この情報は信頼できるのか」「誰が、どのような目的で発信しているのか」を考える習慣をつけましょう。また、お子さんの年齢に合った分かりやすい本やアプリを使って、情報を正しく判断する力を一緒に育てていくのも一手です。
デジタル社会では、目的に合ったツールを選ぶことが大切です。保護者様はお子さんの年齢や成長に合わせて、役に立つアプリやサービスを選びましょう。たとえば、小さなお子さんには想像力を伸ばす遊びができるアプリ、小学生には学校の勉強を助けるデジタル教材など、お子さんの成長に合わせたものを選ぶのがおすすめです。また、フィルタリングソフトの活用や位置情報の設定など、安全に使うための機能も確認しておくのが大切でしょう。
お子さんがデジタル機器を使い始める前に、家庭内でのルールを明確に設定しましょう。使用時間や場所、アクセスできるコンテンツについて、お子さんと話し合いながら適切なルールを作るのがおすすめです。一方的な制限ではなく、なぜそのルールが必要なのかを説明し、お子さんの理解と協力を得ることがポイント。また、ルールは定期的に見直し、お子さんの成長や状況に合わせて柔軟に調整することも大切です。
デジタル機器に触れる時間が増える中、実際に体を動かしたり人と直接関わったりする経験は子どもの成長には欠かせません。家族での対話、公園での遊び、紙の本を使った読書など、画面から離れた活動を日常に取り入れましょう。
たとえば「食事中はスマホを使わない」「就寝前の1時間はデジタル機器を使用しない」といったルールを設けるのも効果的です。オンラインとオフラインのバランスがとれた生活習慣が、お子さんの心身の健やかな成長を支えます。
スクリーンタイムとは、デジタル機器の画面を見て過ごす時間のことです。この時間を適切に管理しないと、お子さんがデジタル機器に依存するリスクが高まります。長時間の利用は、睡眠や視力への悪影響、運動不足などの問題を引き起こす可能性があります。年齢に応じた適切な利用時間の目安を設け、機器に搭載されている時間制限機能なども活用しましょう。何のために使うのかという目的も大切にし、質の高いデジタル時間を心がけることが重要です。
インターネットには目に見えない危険がたくさんあります。たとえば、ネット上で子どもたちに近づき、優しい言葉をかけて信頼させ、個人情報を聞き出したり実際に会おうとしたり。また、一度ネットに投稿した写真や情報を勝手に悪用されてトラブルになったり、悪意のあるサイトからウイルスに感染したりすることもあります。こうした危険を子どもたちに説明し、困ったときにすぐ相談できる関係づくりの構築が大切です。
これからデジタル機器を扱う子どもたちにとって、最終的にはお子さん自身が適切に利用できるような自己管理能力の育成が重要です。小さな頃から段階的に責任を持たせ、自分で考えて行動する機会を増やしましょう。低学年のうちは保護者様と一緒にインターネットを使い、徐々に自分でサイトを選んだり、時間を管理したりする経験を積ませます。失敗があっても一方的に叱らず、「どうすれば良かったか」を一緒に考える姿勢が大切です。

これまで見てきたように、デジタル化は私たちの生活に多くのメリットをもたらす一方で、子どもたちが健全に成長するための適切な対策も必要です。デジタル機器の正しい使い方を学び、情報を見極める力を養うことは、これからの時代を生きる子どもたちにとって欠かせないスキルです。
プロクラでは、子どもたちがプログラミングを通じて論理的思考力や創造力を楽しく身につけられる環境が整備されています。子どもたちは自分のアイデアを形にする過程で、自然とデジタルリテラシーも高めていけるでしょう。
まずは無料体験レッスンで、お子さんがどのように学び、成長するのかをぜひご覧ください。お子さんの可能性が広がる第一歩となるでしょう。
COLUMN